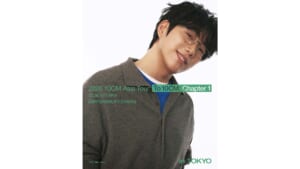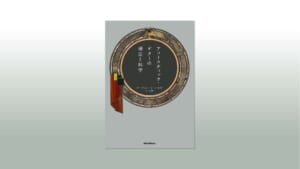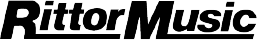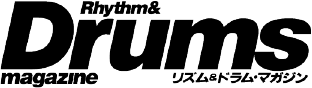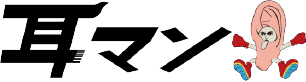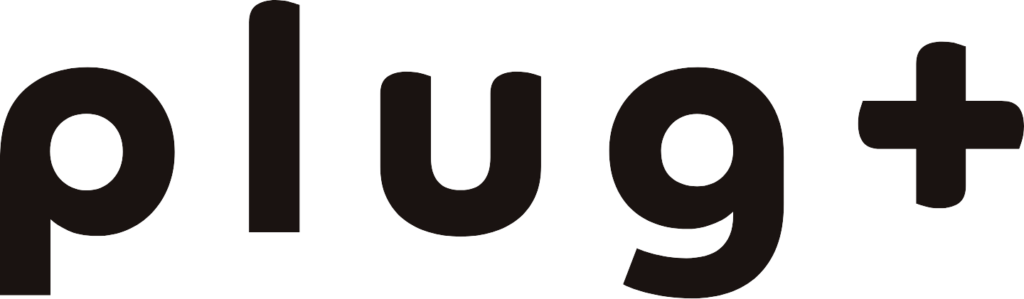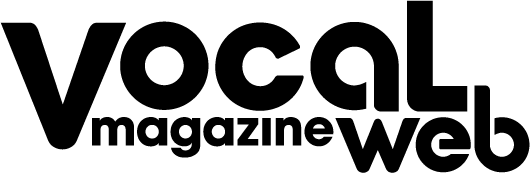僕は、自分でも認めますけど、完璧主義なので
──ギターのプレイ面で、レコーディングで意識していたことはありますか?
ギターがひとりしかいない曲が多いので、間違えてはいけないっていうのはありましたかね(笑)。メンバーもそれぞれプレッシャーが大きかったと思うんですけど、それは当然僕もありました。
あとは、音選びを考えながらやっていきましたね。例えば「化け物が行く」は、原曲キーが高いので、僕のキーに合わせるとなるとかなり下げないといけなくて。そうすると押さえるところが違うので、鳴る響きも変わるじゃないですか。
それにキーを下げすぎると、上げるほうが早くなって結果上げることになりますよね。もうちょっと低い響きのはずなのに、ギターは高いところで鳴らさなきゃいけなくて、全然味が出ないっていう悩みがあって。それは最後まで悩んでいましたね。
“自分らしさって何だろう?”っていうところをちゃんと突き詰めないといけない
──「Shangri-La」では大橋さんがいろんな楽器を担当していますね。
これは一番最後に作業した曲なんですよ。もう1曲ぐらい入れておこうかなと思って。だから時間がなかったんです(笑)。
──この曲のイントロは、アコースティック楽器だけでグルーヴを出しているのがすごくカッコ良いです。
サビだけそれっぽくすればいいかなと思っていたので、遊ぶ方向でいきましたね。ただ、“1本マイクコーナー”の現代の先駆者であるパンチ・ブラザーズのサウンド作りをかなり追っていて、そっちの方向に持っていけたらかっこいいなというのは、この曲で特に思っていました。
──「Pi Po Pa」のアレンジはどのように完成させましたか?
「Pi Po Pa」も2024年のライブでやったんですが、やっていて面白すぎて。もともと隙間が多い曲で、原曲のこの音はバンジョー、この音は打楽器、この音はマンドリンっていうのがあって、ベースはほとんどそのままだし、ドラムもわりとすぐにイメージができてっていう奇跡的なバランスの曲なんです。“ちょっとやってみよう! せーの”ってやった瞬間すぐにイメージどおりになりましたね。
──「新宝島」は、“1本マイクコーナー”でマイクと楽器との距離で音量を調節しているような質感を感じました。
ライブならソロの時にマイクに近づいていったりしますけど、音源だとミックスでなんとでもなってしまいますからね。でもせっかくこのコンセプトでやっているので、より近づいたっぽくしているかもしれないです。ミックスはほぼ自分でやっているんですけど、うしろにいるべき人はルームをちょっと増やして、前にいる人は少なめにしていますね。
──「りんごの木」、「そんなことがすてきです。」は、セルフ・カバー曲となりますが、今作において再解釈、再構築したことはありますか?
バンドでやるので、それぞれのアイディアや持ち味を活かすことができたらいいんだろうなっていうのはありましたね。
あと、原曲には入っていないアレンジを加えたりもしています。「そんなことがすてきです。」は、サビのあとをちょっと伸ばしたりしました。
──今作のカバー・アレンジにおいて、原曲の良さを残しながらアレンジで広げていくためにどんなことを意識しましたか?
原曲と同じことをしても意味がない、でもその良さを絶対に消してはいけない。なおかつ、“自分らしさって何だろう?”っていうところを突き詰めないといけないので、そのバランスですよね。
今回はフル・アコースティックっていう縛りもあったので、「新宝島」のベースなどはすごく悩みました。ウッドベースなので、あまり音数を増やすべきじゃないみたいなところがあるんですよ。全部の楽器がそうなんですけど、僕の中にこういう方向に持っていけたらいいなってイメージがぼんやり、時にははっきりとあるのでっていう感じですね。
──レコーディングで使用したギターは?
「Shangri-La」はマーティンのOM-28(OM-28 Modern Deluxe)、「そんなことがすてきです。」と「化け物が行く」は00-21(CTM 00-Style 21)、「新宝島」がD-28 Marquis、「KAAMOS」はローデン(O-22C)です。あと、「りんごの木」のマーティンD-42と「Pi Po Pa」のバンジョーは高木(大丈夫/mandolin, g, etc)から借りたものを使っています。
『MONO-POLY』大橋トリオ
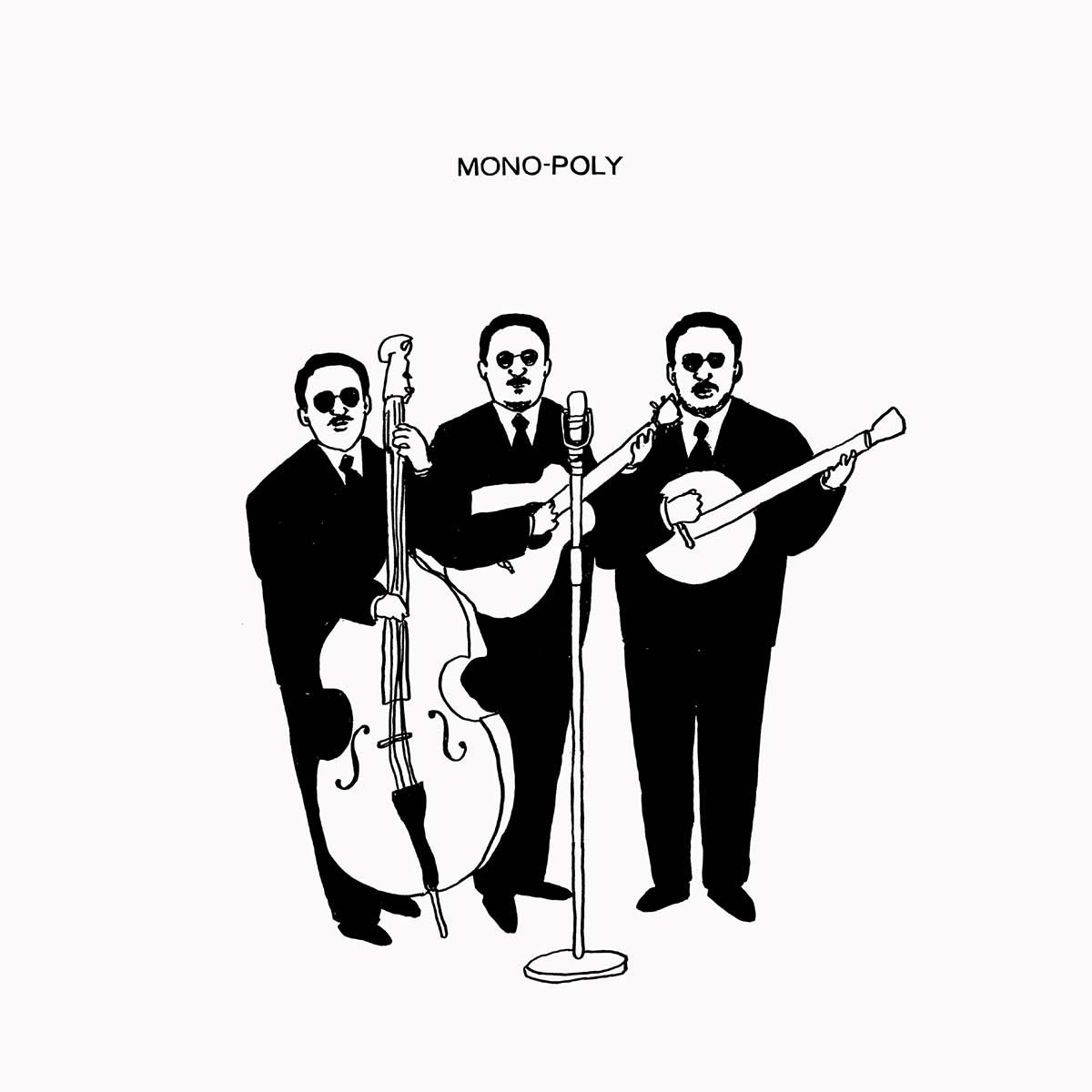
Track List
- そんなことがすてきです。
- Shangri-La
- Pi Po Pa
- りんごの木
- 新宝島
- KAAMOS
- 化け物が行く
avex/RZCB-87174/B(CD+Blu-ray)/2025年8月13日リリース
- 韓国のシンガーソングライター10CM(シプセンチ)が3月28日に東京にて来日公演を開催
- 秦 基博が弾き語りライブ“横浜弾き語り研究会 Vol.1”を開催 中島寂、スーパー登山部Hinaも出演
- マーティンより歴代製品の特徴を融合したアコギ弦、Era Treated Acoustic Guitar Stringsが新発売
- マーティンの新しいRoad SeriesがNAMM 2026で発表 Modern/Retroの2バージョンで計18本のエレアコが新登場
- ギター製作家のアーヴィン・ソモギによる書籍『アコースティック・ギターの構造と科学』が発売
- フェンダーがカスタマイズ・レザー・ストラップをプレゼントするキャンペーンを開催中