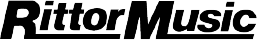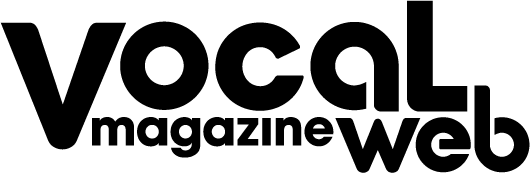メロディを一番前に届けたい
──『First Stage』は初のベスト・アルバムですが、何かテーマなどはありましたか?
“ライブでよく弾く曲を集める”というところが、出発点になっていまして。普段はトラックを作ったりもしていますが、ライブはソロ・ギターがメインなので、その持ち味を形にしたいと思っていました。
──制作に至った経緯を聞かせてください。
2024年が15周年で、節目となる大きなライブを行なったこともあって、次のアルバムを作る前に一旦振り返ろうかなって考えたんです。というのも、2023年に毎週曲をリリースしていった中で、自分の中で作曲法が確立されたというか、“これが自分の持ち味だな”というところが見えてきたんです。それによってできる曲も変わったので、次の作品を作る前に、今までの楽曲を第一弾として切り離して収録したかったんです。
──それぞれの楽曲は最初に収録されたアレンジから変化していますが、ライブで弾いていく中で変わっていったのですか?
そうですね。今ライブで弾いているとおりのアレンジで収録しました。まず、右手のタッチを2015年頃に一気に変えたので、出音が昔のアルバムとは相当違っているのと、アレンジも10数年弾き込んでいった中で少しずつ変わっていった感じですね。
──右手のタッチは2015年にどのように変わったのでしょう?
もともとは小指をボディにつけて指を寝かせて弾くような、カントリー・ギターっぽいスタイルで弾いていたんです。そこから、弦に対して垂直なクラシックのフォームに切り替えて。それによって弾きにくくなった曲もたくさん出てきたので、奏法を変えたりもしたんです。
──今作を聴いていて、全体的にメロディ・ラインや聴くべき部分がはっきりと前に出てくるような印象を受けました。例えば「Sunday Morning」はBPMが下がったことで、速いギャロッピングの存在感が薄まって、楽曲のメロディがより楽しめるようになったというか。
メロディを一番前に届けたいっていうのはありましたね。ソロ・ギターの曲を作る中で、やっぱりメロディを浮き立たせたいっていう思いがあって。
今回はわりとラインの音もしっかり混ぜたんですけれども、音作りもライブで使っている曲ごとのプリセットをそのまま使っているんです。そのプリセットも、メロディがほかのパーツと分離するように意識をして作ったので、生音のタッチもラインの音も、メロディが前に出るようにっていう意識はありました。
あと、全体的にBPMは下げ気味にしています。ライブで何を伝えたいかってなった時に、ギターの美しさとか、そういうところを重視していきたいって思うようになってきたんです。
──メイン・メロディのとらえ方が以前と変わってきたんですね。
そうですね。よりメロディに集中するようになりました。それは打ち込みの曲などを作ってきた経験も生きていて、トラックに対するメロディの置き方を、ソロ・ギターでも自然に考えられるようになってきたんですよ。
初期の頃はリードシートのように、メロディがあってコードがあって〜みたいに考えていましたけど、ボイシングにこだわるようになったり、コードも必ずアタマに持ってこなくてもいいって思うようになったり。
それが顕著なのが「Kokoro」で、メロディを先行させて遅れてコードがやってくるような入れ方をしていて。そうするとメロディがすごく浮き立って聴こえるんです。右手のタッチがどうこう以上に、アレンジでメロディを立てるっていうやり方も覚えてきた感じですね。
クラシックは裏づけされた動きの流れの中に美意識がある
──個人的にニュアンスがすごく変わったと感じたのが「Labyrinth」です。以前のガット・ギターの音色からスティール弦に変わりましたが、ブリッジのパートなどのクラシック感が強まった気がしました。
この曲はもともとクラシックを意識した曲ではあったんですけれども、『Short Stories』(2022年)や松井祐貴さんとのデュオでやった時(『Sound Intersection』収録/2019年)には、言ってもポップスのミュージシャンなので、比較的タイトなリズムで弾いていたんです。
で、昨年からクラシック曲をたくさんアレンジする機会があり、その中で改めて分析すると“クラシックってこんなに曲中でBPMが変わるのか”っていう衝撃があったんです。3年前に映画音楽のオーケストラを経験した時も、1小節前はテンポ50だったのに、いきなり150に変わったり。もっとトラディショナルなベートーヴェンやショパンでも、なめらかにBPMが変わっていく。それがものすごく魅力的に感じて。
それで今回、自分も思い切ってテンポを揺らしてみようってやったのが、うまいこといったというのは少しあります。
──音や弾き方というより、リズム面が大きいんですね。岡本拓也さん朴葵姫さんとの共演など、クラシック・シーンとの交流もありますが、クラシック音楽は井草さんのプレイにどういう影響を与えていると感じますか?
ひとつはルバートなどで、ポップスだと“感覚的に気持ちいいからこう伸ばしてみるか”という考えだったのが、クラシックではちゃんと根拠を持って“メロディがこういう動きだから、こういうルバートをする”って説明できるんですよ。その裏づけされた動きの流れの中に美意識があるなと思って、それを自分の中にも取り入れていきたいなっていう風に変わっていきましたね。
──アコースティック・ギタリストとしての糧になるという視点で、クラシック・ギターをどう学ぶのがオススメですか?
意外と、クラシック・ギターの奏法とかより、曲自体を勉強したほうがプレイに生きるんですよ。一見遠回りに見えるんですけれども、その曲の背景を知ると“こういう音の出し方をしたらいいんだ”っていうのがわかってくる。そこのアプローチを勉強すると違う世界が広けるのかなと思います。
──曲の背景を学ぶことで、どう表現方法に反映されるのでしょうか?
例えばバロック時代、バッハの時代は当時としては明快な感情表現を追求していた音楽ですけれども、今の自分たちから聴くと素朴に聴こえる。テンポの揺らぎも控えめなんですよね。それがロマン派になっていくにつれて、テンポを自由に操って歌い上げるような表現に変わっていくんです。
で、ポップスは時代が進むにつれてビートはどんどんタイトになっていき、打ち込みが主流になると逆に、ディラ・ビート(編注:ヒップホップ・プロデューサーのJ・ディラが生み出す揺れたビート)とか、ヨレたグループが流行ったり。意外とその流れは似ている点もあると思うんです。
そういう曲の背景や作曲者がどの年代に生きたかを知ると、その形式に沿った表現の仕方がプレイにも生きてくると思っています。
コードをズラすことで立体感が生まれました
──「Colorful Night‒Light Waves」の1本とは思えないビート感や、「Mellow Sunset」のルーズなノリなど、近年のトラック・メイクなどで培ったアイディアがソロ・ギターに生きている感覚があります。ビートを作ったり、ギター以外のアンサンブルを追求していく中で、どういった恩恵がありましたか?
2014〜15年頃にEDMにハマっていて、ソロ・ギターでも一切ブレないタイトなビートを出そうと思って作ったのが「Light Waves」で。「Colorful Night」も同じような流れで、最初は打ち込みでEDMっぽいトラックを作りその上にギターを乗せました。それをソロ・ギターにアレンジして『Feel So Good』(2018年)に収録したんですけれども、その時は弾くことに全集中しちゃって、あまり立体的に組み立てられてはいなかったんです。
それがトラックをたくさん作ったことで、コードとメロディを別に同時に鳴らさなくてもいいやっていう考えができるようになって。メロディやコードをシンコペーションさせたことで、パームもすごく入れやすくなって、メロディも弾きやすくなったんですよ。その変化が起きたのが「Colorful Night」と「Mellow Sunset」の2曲です。
それまでは右手の技術だけで、なんとかパームとメロディとコードを同時に鳴らそうと頑張ってたんですけれども、それぞれのパーツをズラすっていう考え方を取り入れて、全部がパズルみたいにうまくハマった感じですね。
「Feel So Good」もサビでそういう感じを取り入れていて。初期は1拍目にドンってメロディが全部きていたんですけれども、それを前やうしろに持ってきたりして。そうすることで立体感が生まれました。
──立体感という言葉がしっくりきますね。トラックが分かれているくらいビートが分離している感覚がありますが、アレンジだけでそこまで変わるんですね。
いやぁ、嬉しいですね。あと、トラックを作る時にドラムの音にすごくこだわっていたので、スネアの良い音をひたすら探したり作っていく中で、“スネアの良い音”というのがなんとなくつかめて、それがソロ・ギターのプレイでも生きた感じもあります。
──それは叩き方が変わるんですか? それとも音作りが変わる?
両方ですね。叩き方も、昔は変にアクセントをつけようとして強く叩いたりして、高音が耳に痛い感じがしてたんです。でも良いスネアって低音が鳴っていて、中低音域にかなりボリュームがあるって知った時に、ギターのプレイもあまり強く叩きすぎずに音を乗せるようになったんです。で、音作りもピーキーにならないような、スネアの音を意識しました。
最初に感動した“ギターの音の美しさ”を追求したい
──レコーディングはどのように行ないましたか?
基本はいつものノイマンのコンデンサー・マイクを使っています。ただ、普段はステレオで2本立てていたのを、今回はライブっぽく聴かせるために初めてモノ・マイク1本で録ったんですよ。それであとからリバーブなどで広げた感じですね。
ステレオのいいところはナチュラルで広がりのある音だと思うんですけれども、モノラルのいいところは力強さや音がガッと前に出る感じ。それと普段ライブで使っているセッティングのラインの音を混ぜたら、すごく良い感じになりました。不思議なのが、結果的にそのほうがステレオ感が強く聴こえるようになったんですよ。
──リバーブなどのエフェクトはプラグインで?
すべてプラグインですね。リバーブはChromaVerbっていうロジックの定番のやつで、Chamberっていうタイプを使いました。それのハイを上げるとシマーっぽく聴こえたりするので、何曲か使いました。EDMで超定番のヴァルハラDSPのリバーブも、「Good Sleep」でシマーをガッツリ、「Sunflower」は数パーセント隠し味的にかけていますね。
──レコーディングで特にこだわった点は?
“音を作りすぎない”っていうことを大事にしましたね。作品として作り込むのは良いんですけれども、CD音源とライブの音がなるべく同じに感じられるようにしたかったので、今回はライブで再現できる範囲の音作りにしました。なので、特殊なプラグインを使ったり、パームの音を持ち上げたりはまったくせず、なるべくEQはフラットで録りましたね。
──ギターはアヌエヌエのLS SEIJI IGUSAの1本に絞ったということですが、その理由は?
最近はずっとアヌエヌエがメイン・ギターで、本当に気に入っているんです。で、くり返しになっちゃうんですけど、これもライブを想定した感じで。普段のライブでは1本でやることがすごく多くて、音や曲の変化でライブを構成しているんです。なるべくその雰囲気にしたかったのと、あとは1本のほうが曲ごとの指のタッチの変化もわかりやすいんじゃないかなって思ったのもありますね。

──同時にタブ譜も発売されますね。
長年僕のことを応援してくださっている方は、楽譜を見た時にその変化に驚かれるんじゃないかなと思っていて。耳で聴いている以上に楽譜上では動かした部分がわかると思います。ソロ・ギターで完コピしていただけるのも嬉しいですし、音源に合わせてセッション感覚でメロディやコードを弾いて楽しんでいただけたら嬉しいです。
──本作を聴いていて、テクニック的にはいくところまでいって、音楽的な表現を深めていくステージに移ったような印象を受けました。タイトル的にも“First Stage”ですが、井草さんが次に目指すステージはどういったものでしょうか?
自分の中で大きく変わったのがそこなんですよ。最初のアルバムを出した時は、“テクニックがすべて!”、“バラードを弾くギタリストなんて信じられない!”ぐらいに思っていたんですよね。実際にライブでもテクニカルな曲や、ものすごく速いBPMの曲ばかり弾いていました。
でも、ギターを始めた頃って別にそこに感動していたわけじゃないんですよね。初めは煌びやかな音に惹かれていたのが、いつの間にかギターを頑張って練習していく中でテクニックに傾倒していってしまった。もちろんテクニックは表現力の土台になる大切な部分ではあるのですが。
ただ、演奏活動を続ける中で、少しずつ最初にギターに惹かれた頃の感覚に戻ってきたような気がします。次に作るアルバムはその最初に感動した“ギターの音の美しさや透明感”を追求していこうかなと思っています。
──では最後に、この作品をどんなふうに聴いてほしいか、メッセージをお願いします。
まず今回はライブを想定した“セットリスト”であり、自分の過去作を振り返った内容でもあるので、とおして聴いてほしいですね。あと、しっかり聴いてもらえるのはもちろん嬉しいんですけれども、散歩中や仕事中にかけてもらえるのもすごく嬉しいです。ライブを想定したと言いつつ、日常に寄り添えるようなアルバムになったらいいなと思っています。
『First Stage』井草聖二

Track List
- Lakeside
- Harvest
- Sunday Morning
- Feel So Good
- Monologue
- Horizon
- Sunflower
- Silk Hat
- Kokoro
- Fireworks
- Colorful Night‒Light Waves
- Midnight Star
- Good Sleep
- Labyrinth
- After the Rain
- Windmill
- Mellow Sunset
sunflowermusic/SI-003/2025年9月17日リリース
- 矢井田 瞳が25周年イヤーを締めくくるアコースティック・ツアーを6月より開催
- 韓国のシンガーソングライター10CM(シプセンチ)が3月28日に東京にて来日公演を開催
- 秦 基博が弾き語りライブ“横浜弾き語り研究会 Vol.1”を開催 中島寂、スーパー登山部Hinaも出演
- マーティンより歴代製品の特徴を融合したアコギ弦、Era Treated Acoustic Guitar Stringsが新発売
- マーティンの新しいRoad SeriesがNAMM 2026で発表 Modern/Retroの2バージョンで計18本のエレアコが新登場
- ギター製作家のアーヴィン・ソモギによる書籍『アコースティック・ギターの構造と科学』が発売