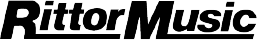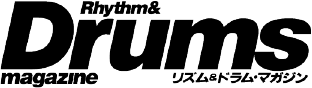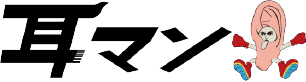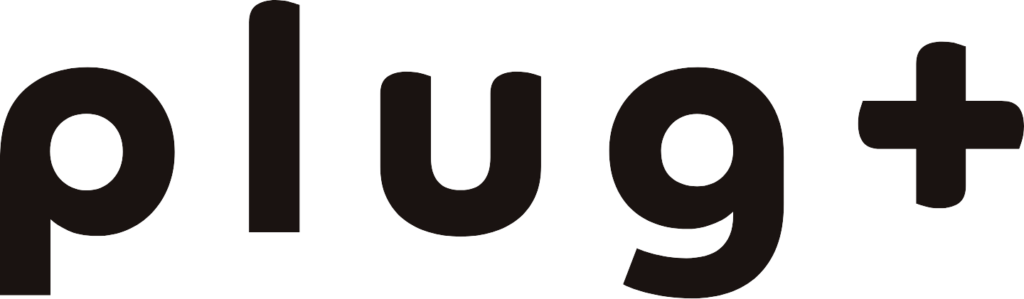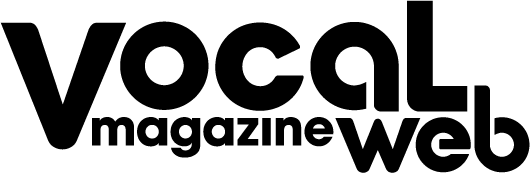“自分の好きなものを出していったほうが良い”と言われて
──まずは、ロック・カバー・アルバム『My Immortal』を作ることになった経緯を教えて下さい。
2019年にアルバム『MEDUSA』を出したあと、今のマネージャーと出会いまして。そのマネージャーと初めて一緒にした仕事がマーティ・フリードマンさんとの共演だったんです。そこでマーティさんに、“クラシック・ギター奏者としてロック好きを隠していた”という話をして。それを聞いたマネージャーからも“自分の好きなものを出していったほうが良い”と言われたんです。それで始まったのが、前半がクラシックで後半はロックの曲を演奏するコンサートの“CLASSIC×ROCK”シリーズですね。
で、ロックの楽曲は、自分で作ったアレンジでやったほうが良いというということになったんです。アレンジは得意じゃなかったんですが、シリーズを重ねていくうちに、自分なりにちょっと慣れてきて。選曲も、クラシック・ギターに合うものがなんとなくわかるようになっていったんです。
そうしているうちに、ロック・アーティストを紹介する連載(月刊誌『音楽の友』の「猪居亜美のGuitar’s CROSS ROAD」)を始めることになったりと、趣味で好きだったロックがちょっとずつ仕事になってきて。
ロックの知識もついて、アレンジや選曲も自分の中でまとまってきたところで、レーベルのフォンテックさんと“全曲ロックのアルバムをやろう”という話になったんです。
──選曲はどのように?
好きなように選んでいいということだったので、これまでコンサートでやってきたものや自分の中でしっくりきたもの、新たにアレンジするものを考えていきましたね。
普段のお客さんの年齢層も考えて80年代の楽曲を入れようという話になって、せっかくなら自分も好きな作品を選びたいので、ガンズ・アンド・ローゼズやメタリカ、オジー・オズボーンを入れました。そこに、自分がリアルタイムで聴いていた2000年代の楽曲も入れた感じですね。
でも実は、曲もギリギリまで迷っていたんです。コンサートでは何回も弾いていたけど、アレンジが気に入らなくて収録をやめた曲もあったりして。クラシックのレコーディングでは、必ず前もって曲を決めておくので、絶対にありえないですが(笑)。
そういう意味では、ここまで自由に、ギリギリまで迷いながら作ったアルバムは初めてでした。レコーディングの時点で、“これならアルバムにできる”と思えたのがあの10曲だったので、予定から変わったこともけっこう多いですね。
──アルバム制作全体で何か考えていたことはありますか?
これまでのクラシック・アルバムを聴いてくださっていた方にはもちろん、メタル・ファン、ロック・ファンの方にも、クラシック・ギターの音を聴いていただくきっかけの1枚になればいいな、ということを目標にしていました。
なので、クラシック・ギターならではの奏法と音色をしっかりと活かしつつ、でも原曲のロック・バンド・ファンの方が聴いた時に“クラシック・ギターで弾くとイマイチだな”と思われないようにしたかったんです。
クラシックを弾く時とは意識が違っていて、それも面白い
──アレンジはどのように進めていきましたか?
自分が原曲から感じたイメージをなんとかそのままギター1本に落とし込むように、というのを念頭に置いて、アレンジを進めていきました。
1本で弾こうと思うと、どうしても省かないといけない部分が出てきてしまうんですが、技術的な理由で音を減らすことはしたくないと思っていて。まず、自分が原曲を聴いた時に印象に残っているフレーズ、ギター・リフやソロは絶対にはずせないですし、あとはメインのボーカルも。そこに、ベース・ラインやドラムのビートを感じさせる伴奏を入れていく。
あとは、どうしても音域的に下げなければいけない、上げなければいけない、というところもあるんですが、聴いた時に違和感がないつなぎ方ができるように、アレンジの中で工夫をして落とし込んでいったり。
──編曲が特に難しかった曲はありますか?
何回もアレンジし直した、という意味で言うと、メタリカの「Master of Puppets」ですかね。あの曲こそ、どうやってギター1本の中に詰め込もう?というのがあったんですが、一番苦労したのはギター・ソロの部分です。
クラシック・ギターの音域にはどうしても収まらないので、オクターブを下げたり。ピック・ハーモニクスにアーミングをかけるところは絶対にできないので、そこはうしろのコードを挟んで、またソロに戻って、みたいなことをやって、なんとか原曲の尺に無理やり詰め込みました。
──ほかのギター・リフについてはどうでしょうか?
ほかのリフに関しても、クラシック・ギターの奏法でなんとか表現したかったので、タンボーラという奏法(編注:右手の親指側で弦を叩いて、パーカッシブな音を出す奏法)でビート感をうまく表現したり。
1枚目のアルバム『Black Star』(2015年)で、アルベルト・ヒナステラという作曲家のギター・ソナタを弾いているんですが、その曲にもギターを叩く特殊奏法があって、それを取り入れてみたんです。
アコギのスラップのように叩くと、クラシック・ギターでは音が間抜けになってしまうんですよね。“クラシック・ギターでこういうのなかったかな?”と探していた時に、その奏法のことを思い出して。そうやって、色んなところからアイディアを拝借しながら作っていきました。
──以前から演奏していた曲もあると思いますが、アルバム収録にあたってアレンジを調整したところもありますか?
クラシックでは譜面どおりに一音も間違えず弾くことを意識しているんです。今回も楽譜は書いているんですけど、“ここに、この音が入っていたほうがノリが出るな”というところは、その都度変えながら弾いていました。
メロディ・ラインやギター・ソロも、微妙にチョーキングしていたり、ビブラートを大きくかけたりしていると、半音上と半音下のどちらとも取れる、みたいなことがあったので、そういったところは元々書いていた楽譜から変えながら弾いたり。
レコーディング後も、ライブで弾きながら“こっちのほうが原曲に近いかな”とか“なんとなくこっちのほうが今はビート感が出る”みたいに変えているんですよ。クラシックを弾く時とは意識が違っていて、それも面白いですね。
盛り上がるんですよね、あの「紅」を弾くと
──エレキ・ギターやボーカルなど、それぞれの音色を表現するうえで気をつけたことはありますか?
それぞれのボーカリストの発音や言葉のニュアンスをそのままメロディとして表現できるようにイメージすること。ギター・ソロも、エレキ・ギターのサウンドをイメージして、何回も何回も楽曲を聴きながら作っていきました。
ギターならではのアーティキュレーション、歌ならではのアーティキュレーションを、原曲を何回も聴いて、“こういう言葉だったな”、“こういう発音だったな”、というのを表現できるように努力しましたね。
──例えばガンズ・アンド・ローゼズのアクセル・ローズと、メタリカのジェイムズ・ヘットフィールドではどう弾き分けるんですか?
それぞれのボーカルの出し方はかなり意識しました。アクセル・ローズは、「Sweet Child o’ Mine」だとわりと優しい歌い方をしているので、弾く時もその柔らかい声が表現できるように、とか。
メタリカの「Master Of Pupputs」はガーっと歌う系なので、爪のアタックをガツンと当てたり。そういう風にアプローチを変えながら、それぞれのボーカルの感じを表現していきました。
──エヴァネッセンスの2曲は、原曲だとピアノの旋律が多く出てきますが、ピアノの音色も同じようにイメージしながら演奏していますか?
そうですね。ピアノの音はクラシック・ギターに近いと思っていて、エヴァネッセンスの2曲はどちらかというとやりやすかったです。曲もクラシカルな雰囲気のバラードなので、表現しやすかったかなと思います。
──X JAPANの2曲は、峯吉奏典さんのアレンジを採用していますね。
“CLASSIC×ROCK”のシリーズを始めた頃、X JAPANの楽曲をやりたくて、自分でアレンジをするか、ほかの方のアレンジを使うかを考えていたんです。その時にたまたま峯吉さんの動画を見つけて。
ほかの選曲を見ても、自分と音楽の好みが合うというか、音楽的な感性が合いそうな方だなというのもあって、SNSでご連絡したところ、“ぜひ使って下さい!”と、言ってくださったんです。
自分とは全然違う音の選び方だったり、原曲へのリスペクトが伝わるアレンジがすごく素敵で。あとは、ギターならではの弾き方ですね。トレモロをうまく使ったり、ギター・ソロの部分はアルペジオだったり、クラシック・ギターでかっこいい表現ができるアレンジですし、“ギター1本にそういうまとめ方もあるのか!”と。
自分のアレンジだけでも良いんですが、ちょっと違う発想のアレンジが入ってるとそれはそれで面白いものになるかなと思って。やっぱり盛り上がるんですよね、あの「紅」を弾くと。
クラシック・ギターに挑戦するきっかけになれば嬉しい
──レコーディングに使用したギターについて教えて下さい。
メインでずっと使っている、マーク・ウシェロヴィッチという製作家のギターで収録しました。伝統的なクラシック・ギターの音というよりも、前にストレートに音が飛ぶような、モダンな音色が特徴です。
我々の世代には、音量が大きい楽器を求めるギタリストが多いんですが、私もそうで。製作家自身も、クラシック・ギターが音量面でマイナスになってしまう部分を改善したいという思いがあったようで、トラディショナルな作りではあるんですけど、かなり工夫して大きな音が出るようになっています。
それに加えて、弦はサバレスで、上がナイロン弦、3弦だけカーボン弦という組み合わせで弾いていて。これも柔らかい音というよりは、どちらかというとストレートでクリアな音が出る弦を使っていますね。
──レコーディングはどのように行ないましたか?
1枚目、2枚目のアルバムを録った時と同じディレクターさんだったので、もう信頼して、という感じでした。今回は、埼玉県富士見市にあるキラリ☆ふじみで録ったのですが、お客さんが入っていない音楽ホールってすごく響くんです。その自然な響きを活かして録りましたね。
──収録楽曲をコピーしてみたい方も多いと思います。何かアドバイスをいただけますか?
やはり大事にしてほしいのは“ビート感”ですね。私もクラシック出身ですが、クラシック的に真面目に弾いてしまうと、原曲の疾走感が出ないので、そこはいつもすごく気をつけています。きっちり弾くというよりも、スピード感を優先しながら……。
ただ、やりすぎると雑になってしまうので、決して雑にはならないように。クラシック・ギターは発音が難しく、雑に弾いてしまうと不完全な音だらけになってしまうので、そこは気をつけながら、前のめりなロックならではの疾走感を意識することがポイントだと思います。
──今回は初のロック・カバー・アルバムとなりましたが、第2弾について考えていたりしますか?
えっと……——次はもう完全に考えていて(笑)。まだ具体的に決まっているわけではないですが、この曲をやりたいという候補がいくつかあるんです。それがいつになるかはまだ全然わからないですけど、考えています。
──最後に、今回のアルバムで注目してほしいポイントを教えてください。
アコギでのアプローチとは違う方向のアレンジになっているのですが、クラシック・ギターならではの音色や奏法というのは、きっとアコギ・ファンの方にも楽しんでいただけるんじゃないかと思います。
“ザ・クラシック・アルバム”だとちょっとハードルが高いなという方にも、“あ、ロックをクラシック・ギターで弾いてるんや!”という感じで、気楽にアルバムを手に取ってもらえたらと思いますし、クラシック・ギターに挑戦していただけるきっかけになれば嬉しいです。
『My Immortal』猪居亜美
Track List
- Sweet Child O’ Mine(Guns N’ Roses)
- Lithium(Evanescence)
- My Immortal(Evanescence)
- Endless Rain(X Japan)※
- 雨のオーケストラ(MUCC)
- 紅(X Japan)※
- Goodbye to Romance(Ozzy Osbourne)
- Dee(Randy Rhoads)
- Master of Puppets(Metallica)
- Numb(Linkin Park)
編曲:猪居亜美
※編曲:峯吉奏典
録音:2023年8月22-23日 富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ
関連リンク
公式HP:https://www.ami-inoi.com/